
しおんのDIY
先日、しおんの相談所に突然、弊社社長が木材を持ち込んできました。 ノコギリやスケールを持ち出して作業を始め・・ あっという間に業務で使う台を作ってしまいました。 ちょっとしたものから、こんな大きなものまで、業務に使う色々 […]
- 相談所のスタッフブログ

先日、しおんの相談所に突然、弊社社長が木材を持ち込んできました。 ノコギリやスケールを持ち出して作業を始め・・ あっという間に業務で使う台を作ってしまいました。 ちょっとしたものから、こんな大きなものまで、業務に使う色々 […]

普段、和服を着ることが少なくなってきた現在、お葬式の場もほとんどの方が洋装ですが、 喪主や近親者が女性の場合は、和服をお召しになる方も多くいらっしゃいます。 しおんでは、和服をお召しになる際の着付け、 また、着物のレンタ […]

大和斎場にてお葬式のお手伝いをさせていただきました。 この度は、故人様のゆかりある皆様にご参列していただく『一般葬プラン』のご依頼でした。 祭壇は、式場の白木祭壇を利用して、壇上を生花でいっぱいにしました。 端まで全て青 […]
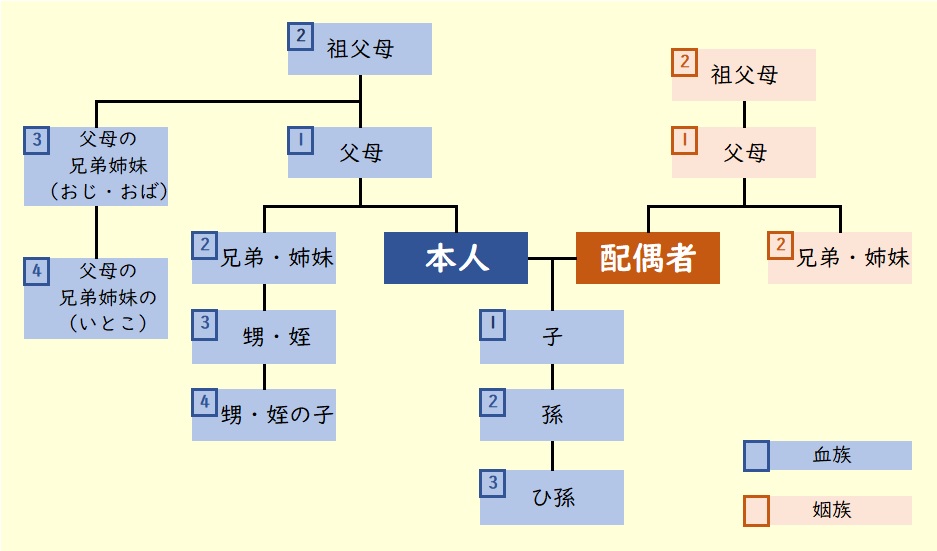
新しい年がはじまって1週間が経ちました。 昨年、私たち葬儀社がご縁のあったお客様は、この最初のお正月を“喪中”に迎えています。 今回の“豆知識ブログ”は「喪中」について、 お客様からよく伺う質問をいくつか紹介したいと思い […]

新しい年がはじまりました。 私たちの仕事上「お正月休み」というものはなく、 年中無休でやらせていただいておりますが・・ 新しい年のはじまりは、やはり身の引き締まる思いがいたします。 〝年中無休〟といえば、私たち葬儀社だけ […]