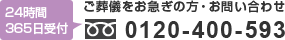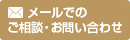夏のはじまりを感じる日 |立夏
カテゴリー:季節の彩りカレンダー
あっという間に5月がやってきましたね。📅
ゴールデンウィークのこの時期は、お出かけやリラックスした時間を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか? 🙂
さて、今回の季節の彩りカレンダーブログは、夏のはじまりを告げる「立夏」についてご紹介したいと思います。
この記事のポイント
・立夏とは?
・立夏はどうやって決まるの?
・立夏の由来
・旧暦と新暦の違いと季節感のズレ
・立夏にまつわる風習や行事
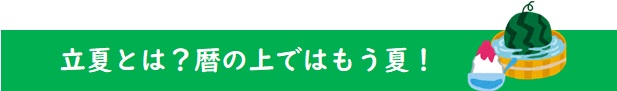
「立夏を迎え、夏を感じる頃となりました。」
こんな挨拶文を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
「立夏」とは、暦の上で夏の始まりを告げる節目の日のことです。「二十四節気」のひとつにあたり、例年5月5~6日頃から始まります。
~ 今年の立夏は 5月5日 から ~🎏
ちなみに、2025年の立夏は5月5日からです。
この時期になると日差しが少しずつ強くなり、木々の緑があざやかさを増し、風にも初夏の香りが感じられるようになります。
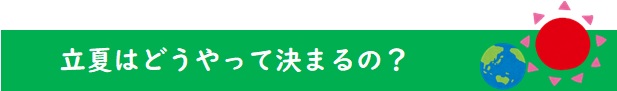
立夏を含む二十四節気は、太陽の動きに基づいて決められています。
地球が太陽の周りを回る1年を360度に分け、太陽がその45度の位置に来た時が立夏とされるのです。
昔の人々はこの太陽の動きを感じ取り、季節の目安として大切にしてきたんですね。
毎年少しずつ日付が前後するのも、そんな天文学的な仕組みに基づいているからなんです。

奈良時代や平安時代にかけて、中国から伝わった二十四節気が暦に取り入れられたのが始まりとされています。
当時の日本では、天皇や貴族たちが季節の節目を意識した行事や儀式を行っており、二十四節気が季節の移り変わりを知るための基準として使われるようになりました。
その中で「立夏」も、夏の始まりを告げる節目として暦や行事に取り入れられ、やがて庶民の生活にも広まっていきました。
立夏を含む二十四節気は、田植えや衣替えの目安となり、人々はこの暦をもとに季節の移ろいを感じ取っていたのです。
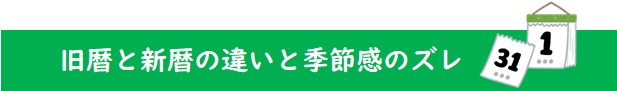
立夏が現在の5月上旬になったのは、明治6年(1873年)に旧暦から新暦に変わった時です。
それ以前は旧暦に基づいていたため、立夏も旧暦の4月に訪れていましたが、新暦に移行したことで、5月上旬が立夏とされています。
旧暦の頃に比べると立夏がやや遅くなりましたが、現代ではこのタイミングを「少し早い初夏を感じる節目」として親しまれています。
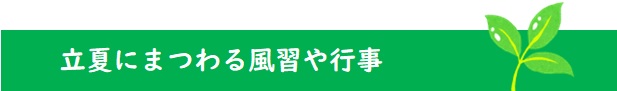
夏の始まりを告げる立夏は、昔から様々な風習や行事が行われてきました。
ここでは、代表的なものをご紹介します。
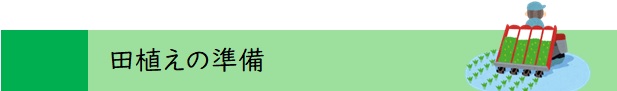
地域により異なりますが、立夏の頃は田植えの準備が始まります。
この時期、農作物の成長を祈る「御田植祭」が各地で行われ、豊作を願う風習があります。
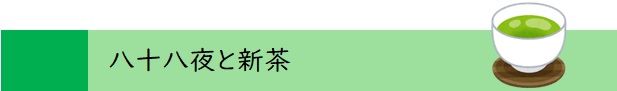
立夏の少し前の「八十八夜」は新茶の季節として知られていますね。
新茶は「無病息災」や「長寿」の願いを込めて多くの方々に飲まれています。
また、茶摘みの行事が各地で行われています。

立夏の時期に行われる端午の節句は、男の子の健康を祈る日です。
鯉のぼりや五月人形を飾り、また地域によっては菖蒲湯で邪気を払う習慣があります。

立夏の頃の風は「薫風」と呼ばれ、さわやかな香りが漂うといわれています。
自然の変化を感じる風習として、薫風を感じながら散歩するのも楽しみの1つです。
~ ご覧いただきありがとうございました ~
立夏は自然の中で新たな季節の始まりを感じる大切な日です。
田植えや新茶、端午の節句など、立夏にまつわる風習や行事は、どれも日本の豊かな伝統を感じさせてくれます。
季節の移り変わりを楽しみながら、私たちも少しずつ初夏を感じてみるのもいいかもしれません。
日常の中で、風や匂い、自然の音に耳を澄ませながら、立夏の魅力を感じていけたら素敵ですね。
これから訪れる夏が、皆さまにとって心地よいものとなりますように。