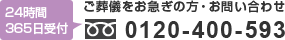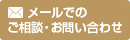100年前のお葬式に参加してみた
カテゴリー:\New/ しおんの“もしも”研究室
もし、タイムスリップして100年前――
大正〜昭和初期の頃に葬儀のお手伝いをすることになったら、どんな一日?
今とは、道具も場所も考え方も、まるで違う時代。そんな中で、人々はどのように大切な人を見送っていたのでしょう?
今回の、しおんの“もしも”研究室は「100年前のお葬式」をテーマに、当時の一日の流れをたどりながら、現代との違いをご紹介していきます。
しおんの“もしも”研究室は、
「もしも〇〇だったら?」という、ちょっと不思議なテーマをきっかけに、葬儀や仏教、宗教儀礼をやわらかく・わかりやすくお届けしていく新シリーズです。ぜひ、お気軽にご覧ください 🙂
※お葬式の形式は、地域や宗派によって異なる場合があります。あらかじめご理解の上、ご覧いただけますと幸いです。
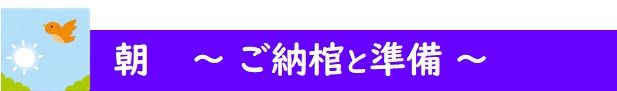
▶ 100年前の朝 ☀
ご自宅の仏間で故人様が安置されています。納棺は、近所の方や親戚たちが手伝いながら、白装束を着せ、丁寧にお体を整えるところから始まります。
棺は今のような布張りではなく、シンプルな木の箱。副葬品(故人の愛用品など)も一緒に納める風習がありました。


現代では、納棺師や専門スタッフが中心になって納棺します。故人様のお顔とお体を丁寧に整え、時には「湯灌(ゆかん)」なども行います。
※現在では、昔ながらの湯灌の儀式を行うことは少なくなり、簡略化されることも多くなっています。
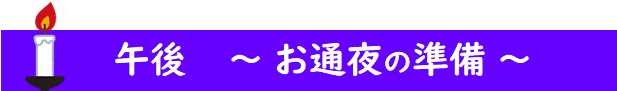
▶ 100年前の午後 🕯
お通夜は近所の人たちの協力で準備が進みます。炊き出しや座布団、提灯など「村や町内全体で支える」という雰囲気。式場ではなく、自宅の座敷に祭壇を設け、故人様は布団の上に安置されている場合もありました。
料理する人、提灯を持って訪れる人、仏前に果物や菓子を供える人―― まさに“みんなで見送る”風景です。


今は葬儀社や会場が準備を整えます。参列者は基本的に短時間の訪問で、宿泊をともなうことはほぼありません。
自宅ではなく葬儀会館でのお通夜が主流となっています。
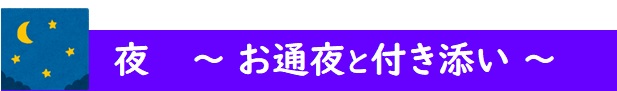
▶ 100年前の夜 ★
通夜が始まると、お経が唱えられ、遺族や近隣の方が交代で線香を絶やさぬように焚きつづけます。「夜通しで線香番をする」という風習があり、誰かが付き添うのが当然とされていました。
みんなで思い出を語りながら、しんみりと、時に笑顔も交えながら夜を越します。


現代の通夜は、だいたい1〜2時間の儀式がが中心となりました。
線香を絶やさないという習慣は薄れ、付き添いも必須ではありません。
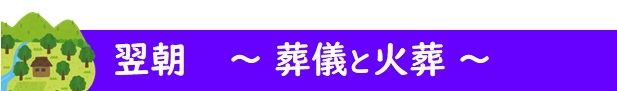
▶ 100年前の朝 ☀
出棺のときは、白木の棺を肩で担ぎ、ご近所や親族が列をなして「野辺送り」へ。
(※野辺送りとは、亡くなった方をお墓や火葬場へお見送りすることをいいます)
時にはお囃子(はやし)が鳴る地域もあり、途中で止まってお経を唱えることもありました。
霊柩車はなく、牛車や人力車で火葬場へ向かうこともあり、火葬場も今のように整備された建物ではなく、野外に簡易な炉を設けて行う地域もありました。


今は式場で葬儀・告別式を行い、霊柩車で火葬場へ移動します。
(火葬場が併設されている式場は徒歩で移動)
時間も限られており、比較的スムーズで静かな流れが一般的です。

~ 昔と今、変わったもの・変わらないもの ~
昔のお葬式は、地域全体で見送り、泊まり込みで支えあうような「みんなの行事」でした。
今は、専門スタッフによって整えられ、遺族が落ち着いてお別れできるように「安心できるかたち」へと変化しています。
でも、どちらにも共通しているのは――「大切な人を、心から見送る」という思いです。時代が変わっても、葬儀が人の心に寄り添う時間であることに、変わりはありません。
その心を、これからも静かに受け継いでいけたらと思います。
~ しおんブログのご案内 ~
しおんブログでは、お葬式の様々なちょっとした豆知識や葬儀事例など、さまざまな記事を毎週掲載しています。
ぜひまたお立ち寄りください。お待ちしています! 🙂
click ▶お葬式の豆知識,よくある質問
click ▶お葬式の豆知識,深堀りシリーズ