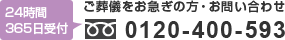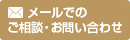意外と知らないお骨上げのこと
カテゴリー:お葬式の豆知識,深堀りシリーズ
「お骨上げ」「お骨を拾う」――
お葬式のあと、ご火葬の場面でよく耳にする言葉ですが、その意味や背景まで知っている方は、意外と少ないかもしれません。
今回の豆知識,深堀りシリーズは、「どうして『拾う』って言うんだろう?」「なぜ二人一組で行うの?」など、これまで特に深く考えたことはなかったけど、言われてみれば気になる、そんな素朴な疑問を検証していきたいと思います。
この記事のポイント
・お骨上げとは?
・「収骨」と「拾骨」の漢字の違い
・収骨の歴史
・なぜ「拾う」というの?
・なぜ「二人一組」で行うの?
・骨壺に入れる順番
・喉仏って実は・・?
・地域差により違いがある
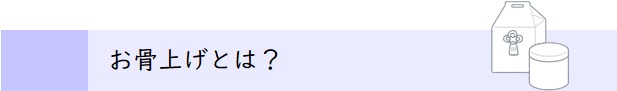
ご火葬後、ご家族の手でお骨を骨壺に納めることを「お骨上げ」または「収骨(しゅうこつ)」と呼びます。
丁寧にお箸でお骨を拾い、壺へ納めていくこの所作には、亡くなられた方への敬意と、最後までご自身の手でお見送りしたいという深い思いが込められています。地域や宗派によって異なる場合もありますが、お骨上げは多くの方にとって、お別れの時間を締めくくる大切なひとときです。
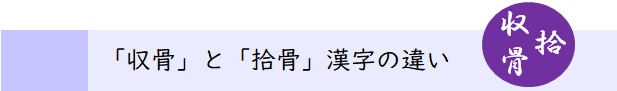
「お骨上げ」や「お骨を拾う」と表現されるこの儀式、正式には「収骨」とも「拾骨」とも書かれます。
・「収骨」は“骨壺に納める”という全体の儀式的な意味を含んだ表現。
・「拾骨」は“お箸で丁寧に拾い上げる”という行為そのものに焦点を当てた表現。
どちらも正しい言い方で、実際の現場では「拾骨」が多く使われますが、文書や式辞では「収骨」と記されることもあります。
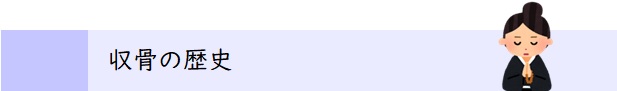
この「収骨」という儀式は、明治時代以降、火葬が一般化する中で徐々に現在の形に整えられていきました。もともとはお骨をすべて持ち帰ることはめずらしく、一部だけをお墓に納めることが一般的だったといわれています。
現代では、ご家族の手で丁寧に拾骨を行い、骨壺に納めるという流れが一般的になっています。
収骨のかたちは時代や宗教、地域の風習によってもさまざまですが、「大切な人を最後まで見届ける」という想いは、いつの時代も変わらないものかもしれません。
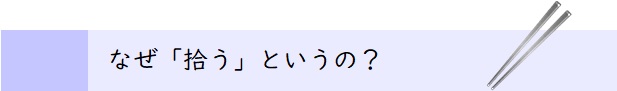
「お骨を拾う」という表現については、実は明確な由来や出典が残されているわけではないそうです。ですが、いくつかの説や背景が考えられていますので、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
![]()
「拾骨」という言葉は、仏教儀礼の一部として使われてきた正式な言葉だといわれています。これが口語として「お骨を拾う」となり、一般にも定着したと考えられています。
![]()
火葬後のお遺骨を箸で一つひとつ丁寧に取り上げるという行為そのものが「拾う」という言葉に自然と結びついたともいわれています。物理的な動作として「拾っている」から、という実用的な理由です。
![]()
「拾う」という言葉には「ひとつずつ丁寧に、大切に扱う」という意味合いも込められているように思います。お遺骨を大切に扱う気持ちを表すために、そうしたやさしい響きのある言葉が選ばれてきたのかもしれません。
「お骨を拾う」という表現は、宗教的・文化的な背景や実際の所作の中で、自然と根づいてきた言葉だ考えられます。はっきりと「これが由来」と言えるものはないものの、お遺骨を一つひとつ大切に手に取る、その気持ちに寄り添うような心のこもった言葉として、日本の文化の中に静かに息づいているのではないでしょうか。
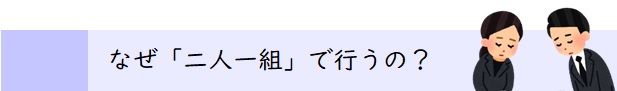
「二人一組でお骨を拾う(収骨をする)」という習わしについても、実はその由来がはっきりと分かっていないようです。いくつかの理由や背景が語り継がれていて、文化的・宗教的な意味合いの中で自然と広まっていったともいわれています。
現在では「二人で拾うのが当たり前」あるいは「収骨のマナー」のようになりつつありますね。
ここでは「二人一組」で行う理由として語られているいくつかの説をご紹介します。
![]()
お骨を二人で拾うという行為は「人はひとりでは生きられない」「亡くなってからもご縁を大切にする」といった仏教的な価値観に通じるとされています。
→ 特に「一人ではなく、誰かと一緒に丁寧に送る」という行為そのものに、ご縁・感謝・支え合いの意味が込められているという説です。
![]()
日本では「箸から箸へ物を渡す」こと(いわゆる箸渡し)は、収骨の場所以外では縁起が悪いとされ、タブーとされています。これは収骨でしか行わない特別な儀式だからこそ。
→ この特別な動作を誤って日常で行わないようにするために、あえて二人一組で行うようになったという説があります。
![]()
箸渡しは“橋渡し”と音が同じなので、あの世とこの世をつなぐ意味がある、という説もあるそうです。言葉の響きから来ているという、少し不思議で興味深い考え方ですね。
収骨の行い方については、明確なルールや起源があるわけではありませんが、
「大切な人を、大切に見送る」「一人ではなく、誰かとともに手を添えて送る」
という心の在り方が自然と“二人一組”という形に表れてきたのだと考えられます。「二人で向き合いながら、大切にお骨を拾っていく――そこには“人と人のつながり”や“感謝の気持ち”が受け継がれているのかもしれません。
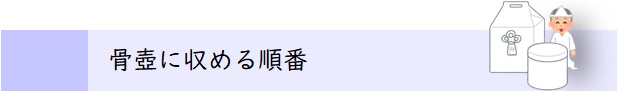
~ 足から頭へ 順番にも意味がある ~
お骨壺にお遺骨を納める順番にも、昔からの習わしがあります。多くの場合、足の方から順に、最後に頭(喉仏)をお納めするのが一般的です。
これは「自然な姿で眠るように」という意味合いがあり、仏教的な考えに由来するともいわれています。
※宗教・宗派、地域により異なることがあります
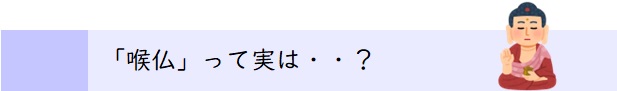
~ 知っておきたい小さな豆知識 ~
お骨上げの際に「これが喉仏ですよ」と言って火葬場の職員がお骨をお見せする場面があります。多くの方が、仏様が座禅を組んでいるように見えるその形に驚かれ、手を合わせてじっと見つめられます。
実はこの喉仏、厳密には“喉”ではなく「第二頸椎」と呼ばれる首の骨の一部です。特徴的な形をしており、昔から「仏さまの姿に似ている」と大切にされてきました。
※ただし、ご火葬の状況によっては形がくずれていたり、見つからない場合もあります。喉仏がなかったとしても、決して不思議なことではありませんし、それによってご供養の心が変わることもありません。
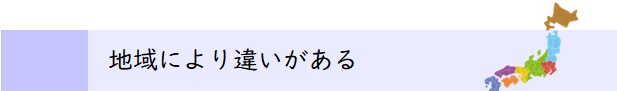
お骨上げの作法には、実は地域や宗教によってさまざまな違いがあります。
先ほどご紹介したように、喉仏を大切にする地域もありますし、ご遺族の代表の方だけが行うこともあるなど、地域によってお骨上げのかたちはさまざまです。また、関東では一般的にすべてのお骨を骨壺に納めるのに対し、関西では骨壺が小さく、一部のお骨のみを納めることが多いようです。
さらに、同じ都道府県内であっても、市区町村の火葬場の運用や条例によって対応が異なる場合もあります。また、宗教や宗派によっても作法に違いが見られます。
こうした違いは「どちらが正しい・間違っている」というものではなく、それぞれの土地や宗教の文化や考え方に基づいた大切な習わしです。お遺骨を丁寧に扱い、故人を敬う気持ちがあれば、その土地のやり方を尊重することが何より大切だといえるでしょう。

~ ご覧いただきありがとうございました ~
今回の豆知識,深堀りシリーズでは、お骨上げについてご紹介しました。お骨上げという儀式は、一見すると形式的にも見えますが、一つひとつの所作にはやさしさや深い意味が込められているものですね。お葬式の中の一つの場面にも、改めて考えてみると大切な意味があるのだと、私たち自身も学ばせていただいています。「こうしなければ」と思うより「どんなふうに心に残したいか」を大切にしたいですね。
~ 無理せず、その人らしい関わり方で ~
実際のお骨上げの場面では、「お骨を見るのが辛い」や「初めてで緊張してしまって…」と戸惑われる方もいらっしゃいます。小さなお子様などは立ち会わずにお見送りされることも少なくありません。必ずしも全員が参加しなければならないわけではありませんし、無理に手を伸ばさなくても、その場にいるだけで想いはきちんと届く――私たちはそう感じています。
迷いや不安があるときは、どうぞ遠慮なくスタッフにお声かけください。最期のひとときが、ご家族にとって少しでもあたたかい時間となるように、そのお手伝いができましたら、私たちも嬉しく思います。
~ しおんブログのご案内 ~
しおんブログは、お客様からいただいたご質問やご意見をもとにしたお葬式の豆知識やスタッフの日常など、さまざまなテーマの記事を毎週更新しています。
少しでもお役に立つことがあればとても嬉しいです!ぜひお気軽にのぞいてみてください。 🙂
click ▶しおんブログ 記事一覧
click ▶お葬式の豆知識,よくある質問
click▶お葬式の豆知識,深堀りシリーズ