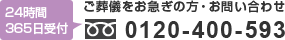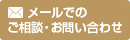どうしてお葬式は“アナログ”なのか?
カテゴリー:業務中のスタッフブログ
ITが進化してもお葬式がアナログな理由とは?
~ 変わらないもの、そして少しずつ変わってきたこと ~
日々、お葬式のお手伝いをさせていただいている中で、ふと感じることがあります。
それは「これだけ世の中がデジタル化しているのに、お葬式の基本は大きく変わらない」ということです。
スマホやキャッシュレス決済、オンライン会議、AI…。
日常生活の中では当たり前になった「デジタル」ですが、お葬式の現場では今もなお、手書きの芳名帳に筆ペン、火を灯すろうそくや線香といったアナログな光景が多く残っています。
今回のスタッフブログは、その理由や背景、そして実は少しずつ変わり始めていることについて考えました。
この記事のポイント
・お葬式が変わらない理由
・少しずつ変わってきていること
・変わらないことにも意味がある
・これからのお葬式に求められるもの
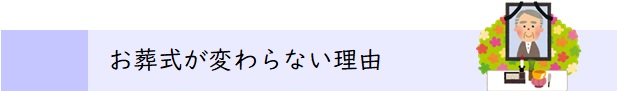
~ 考えられる理由 ~
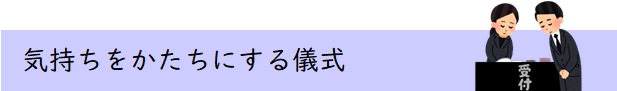
お葬式は、亡くなった方への感謝やお別れの気持ちを表す、大切な儀式です。
焼香や手を合わせるという行為そのものに、人の想いが込められているからこそ「便利なだけ」では、代えられないものがあるのかもしれません。
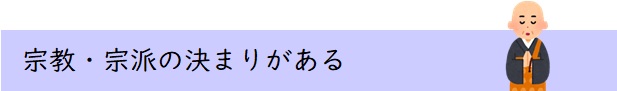
宗教儀礼には、読経や作法など長く受け継がれてきた伝統があります。
ご家族のご希望だけでなく、寺院や宗教者とのやり取りを通じて、自然と「伝統的な形式」が今も受け継がれているという背景があります。
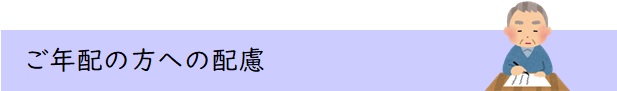
参列される方の中にはご高齢の方も多く、「手書きが安心」「紙の案内の方が分かりやすい」といったご意見も。すべてをデジタルに置き換えるのではなく、誰にとっても分かりやすく、失礼のないようにすることが大切です。
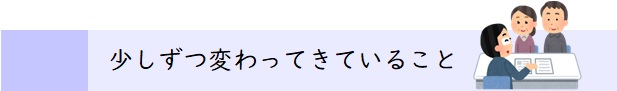
とはいえ、すべてが「昔のまま」というわけではありません。
ゆるやかにではありますが、現代らしく変わってきたこともあります。
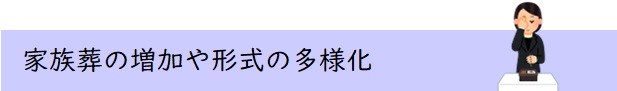
お葬式の規模が小さくなってきているだけでなく、無宗教やお別れ会など、従来のかたちにとらわれない新しいスタイルも見られるようになりました。ご家族の思いや故人らしさを大切にした、さまざまな選択肢が広がってきているのを感じます。
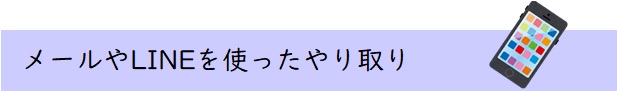
ご家族や喪主の方とのご連絡をLINEで行ったり、打ち合わせに必要なものをメールで共有するケースも増えています。お客様のご希望に合わせて柔軟な対応が進んでいます。
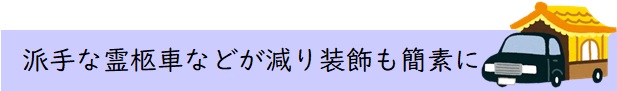
かつては、大きく華やかな花環や、きらびやかな装飾の宮型霊柩車など、いわゆる「派手なお葬式」が一般的だった時代もありました。しかし最近では、そういった装飾はあまり見かけなくなっています。中には、宮型霊柩車の乗り入れを禁止している斎場もあり、その背景には近隣住宅への配慮などもあるのかもしれません。
以前のように目立つことよりも、落ち着きや静けさが重視されるようになり、お葬式のかたちもより時代に合ったものへと、少しずつ移り変わってきているのを感じます。
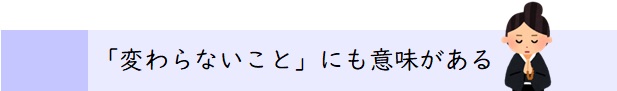
最先端のIT技術がどれだけ進んでも「人を送る」「故人を敬う」という気持ちは昔から変わりません。むしろアナログだからこそ、あたたかさや丁寧さが伝わる場面もあると、私たちは感じています。
これから先、お葬式も時代に合わせて大きく変わっていくかもしれません。
それでもきっと「大切な人を大切に送りたい」という想いだけは、変わらずに残っていくのだと思います。
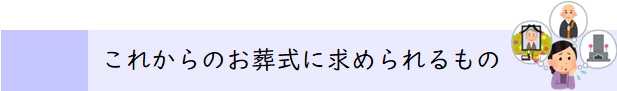
時代の移り変わりとともに、お葬式に対する考え方も少しずつ多様になってきたように感じます。昔から大切にされてきた儀礼やしきたりを尊重しつつも、ご家族の思いや状況に合わせて、かたちを柔軟にしていくことも、これからの時代に合ったあり方なのかもしれません。
「こうしなければならない」という決まりにとらわれすぎず、「その方らしいお見送りとはどんなものだろう」と、ご遺族と一緒に考えていくこと。その姿勢が、これからのお葬式に求められていることのひとつではないかと、私たちは感じています。

・お葬式がアナログなのは、伝統や気持ちを大切にする儀式だから
・宗教やご参列の方への配慮からも、急激な変化はしづらい
・一方で、少しずつ今の時代らしい形へと変化しつつある
・デジタルでは伝えきれない「想い」があるのも事実
これからも私たちは、ご家族の思いに寄り添いながら、かたちだけではない「その方らしいお見送り」をお手伝いしていきたいと考えています。
変わっていく部分と、変わらず大切にしていきたいこと。そのどちらにも目を向けながら、これからのお葬式について、皆さまと一緒に考えていけたらと思います。
~ 関連記事 ~
click ▶キャッシュレス社会でもお香典が現金の理由
click ▶笑い過ぎですか?